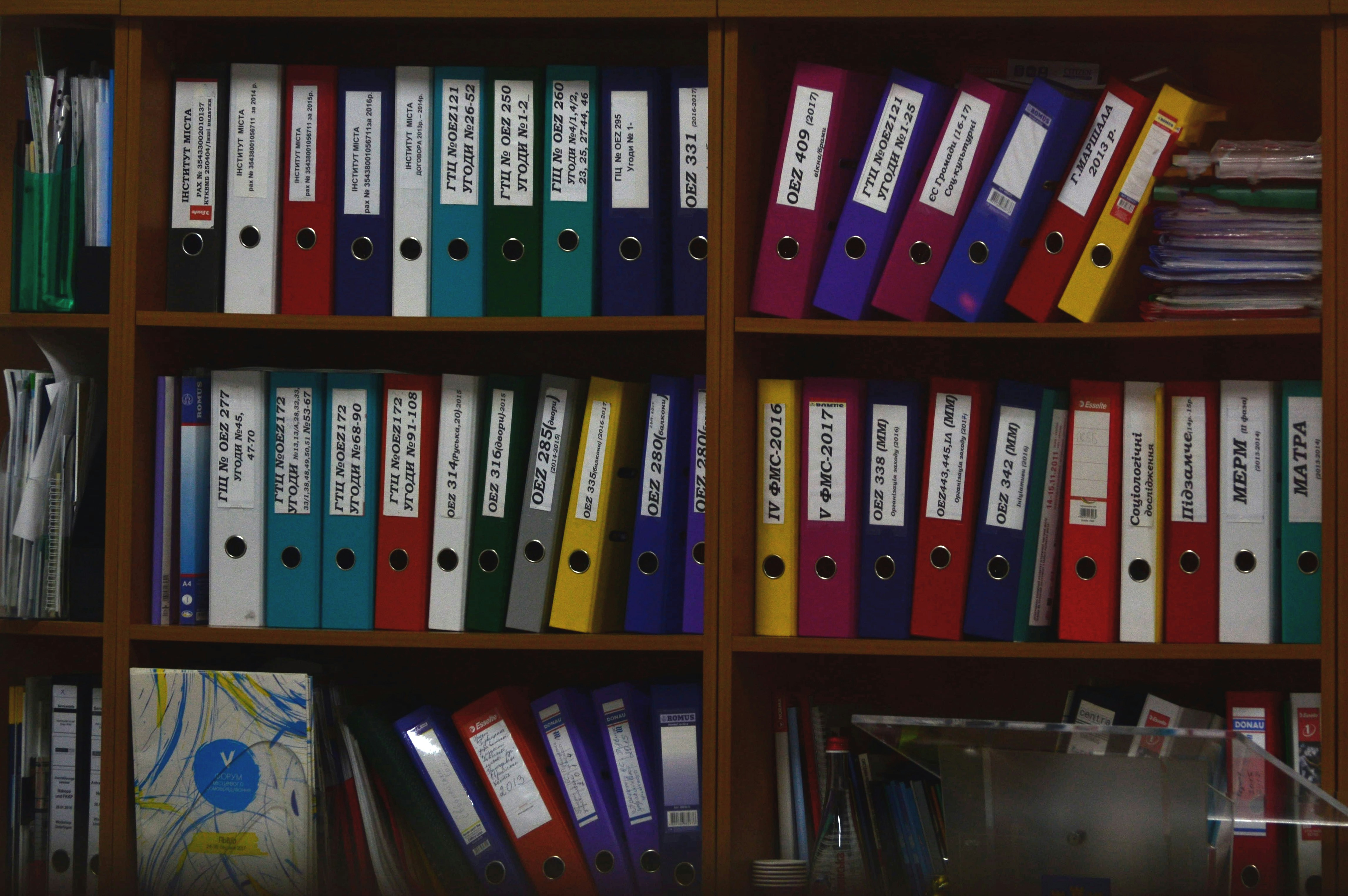Published: Jul 11, 2025 by ONIC Japan
SDN 登場から スキルギャップの危機感 が顕在化してエンジニアの学び場は、危機感を出発点に、クラウドネイティブ、DevOps、そして生成 AI・AIOps へと舞台を移してきました。ここでは、Interop Tokyo で蓄積された育成ノウハウと市場動向をまとめて、ONICが提供する次のフィールドへと展望します。
SDN 技術が商用化して2017〜2019 年は「人が足りない」という切迫感から、OJT やCTF など学びそのものを試行錯誤するフェーズでした。現場はネットワークとアプリの境界を越えるクロススキルを求め、エンジニアは自らの専門領域を横に拡張することで生存戦略を立てて来ました。
2020 年に入ると、IaC (Infra as Code) やDevOps が一気に浸透し、「コードでインフラを操る」ことが当たり前に。ここで学び方は大きく転換します。ツールやフレームワークを追うだけではなく、 自動化を前提に設計する思考 が育成カリキュラムの中心に据えられました。クラウドネイティブが本格化した 2021 年には、可観測性と API 連携が運用負荷を大幅に下げ、学習テーマは「観測・分析・改善」の高速ループをどう回すかにシフトします。
さらに 2023 年以降は、AI/ML とインテントベースネットワークが注目を集め、「どの技術を、どこで、いつ使うべきか」という設計判断力が問われるようになりました。単純なツール習得では差別化できず、エンジニアにはT字型(専門+隣接領域)を超えて、π字型(コード実装 × AI活用 × ビジネス指標)を横断するスキルが求められています。こうした背景には、企業の投資先が SDN 実証からクラウド拡張、そして可観測性・AIOps へと移った資金の流れがあり、「どこにおカネが集まるか」を読むことが育成戦略でも不可欠になっています。
そして 2025 年、生成AI とAIOps が現場で稼働し始め、常時可視化と予兆検知が当たり前の世界が見えてきました。エンジニアは「障害を 起こさない ための運用」を担い、LLM を使ったリアルタイムな根本原因分析(RCA)を武器に、ビジネス価値を直接押し上げるポジションへ進化します。
こうしたテクノロジーの連続的進化の先にONICが掲げるのは、「発見と挑戦が止まらない学習ループ」。SDN ショックをチャンスに変えたように、生成AI 時代を楽しんだ人が先に行ける。そんなメッセージを胸に、次の一手を描くカンファレンスを目指しています。
ONIC 2025 の参加登録や最新ニュースは公式サイトで随時更新中。新しい発見を! 会場でお会いしましょう。
参考:Interop Tokyo カンファレンス エンジニア育成セッションのテーマ変化
| 年 | トピック | 育成フォーカス |
| 2017 | SDN 時代の人材不足 | ネットワーク×アプリの クロススキルが急務 |
| 2018 | スキル標準とアップスキリング | OJT&フルスタック化で現場力を底上げ |
| 2019 | ハードニング & CTF | 競技で鍛える “勝手に育つ” エコシステム |
| 2020 | DX × IaC × DevOps | “NetDevOps”がメインストリームへ |
| 2021 | クラウドネイティブ & 可観測性 | API 連携で運用負荷を劇的削減 |
| 2023 | インテントベース & AI/ML | どこに・いつ技術を当てはめるかが論点に |
| 2024 | GitHub Copilot & 自律チーム | 社内 DevSecOps 文化が市民権を獲得 |
| 2025 | 生成AI × AIOps | 常時可視化と予兆検知が当たり前に |
Photo by Emile Perron on Unsplash