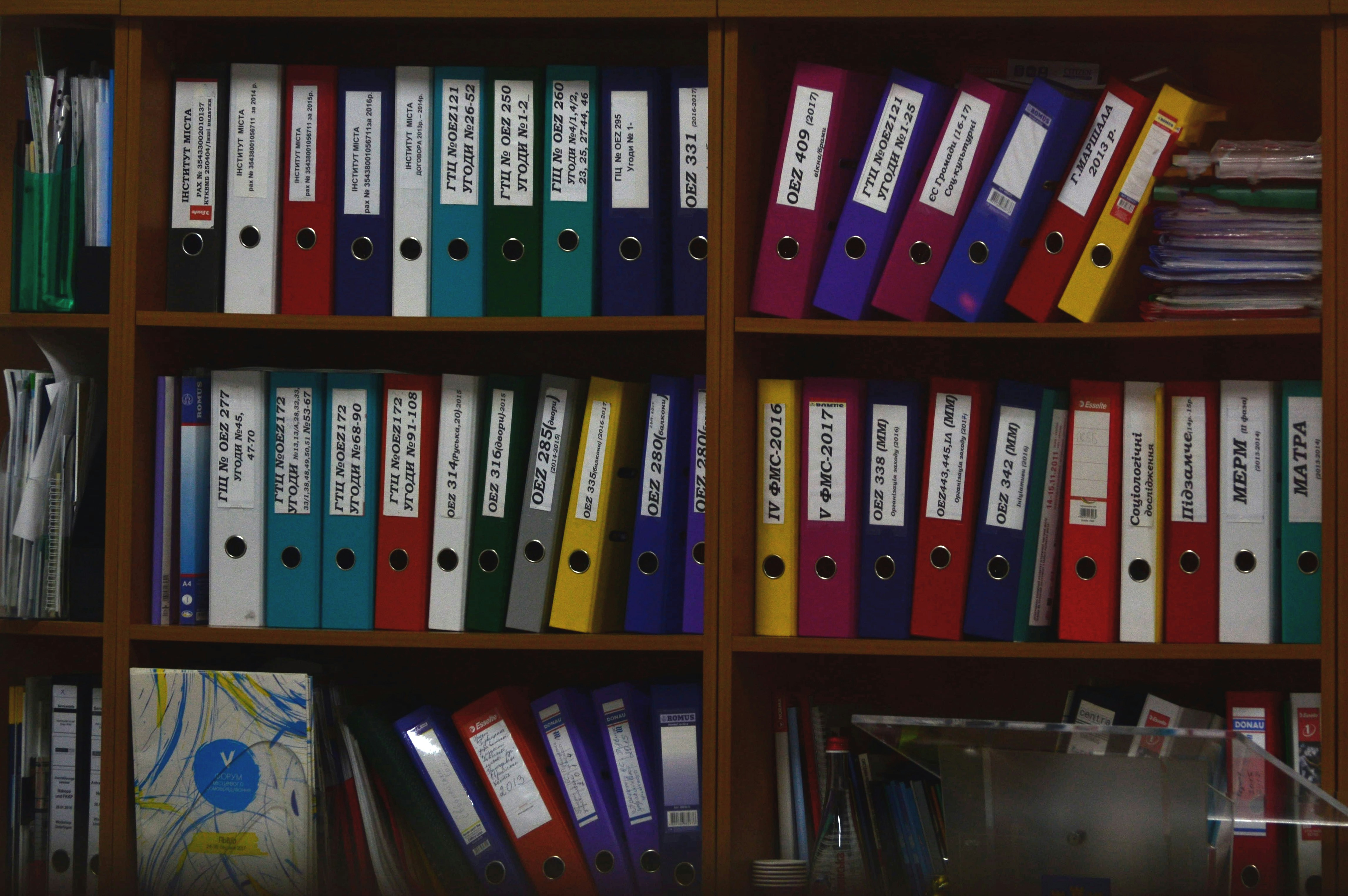Published: Jun 30, 2025 by ONIC Japan
ONICにおけるShowNetセッションは定番となりつつありますが、その歴史を振り返るとSDN Japan時代の2013年から始まっています。 この記事ではその取り組みについて振り返ってみたいと思います。
Interop Tokyo ShowNetでは2012年からSDNに関する様々なチャレンジを行っています。 Openflowからはじまり、IP経路制御技術(Dynamic Routing Protocol)の組み合わせやSegment Routingを用いたプログラマビリティへの挑戦など、様々な実証実験に対する知見をShowNet NOCチームメンバーがONICでも共有してくれて議論を行ってきました。
より柔軟なネットワークを目指した取り組みは、大まかに分類すると以下のようになるかと思います。
- 2012-2013: Openflowを用いたSDNへの挑戦
- 2014-2016: NFV(仮想ルータ)を用いたSDNの拡張
- 2017-2018: IP Routingをフル活用した用いたService chainingなど
- 2019-2024: SR/SRv6を用いたService Chainingや様々な実証実感
こう見返すとネットワークへのプログラマビリティの導入はこれまでかなりの進化を遂げたように思えますし、ShowNetの挑戦は常にその最前線を走ってきたように感じます。 当初はトライアンドエラーの側面もあったと思いますが、ネットワーク側も最近はプログラマビリティを前提とした作りとなってきており、広がりを見せてきています。
この中で毎年、SDNに関わるところでもそれ以外でも様々な挑戦をしてきたShowNetですが、今年もきっと興味深い知見をみなさまと共有しながら議論が進められることだと思います。 11月に軽井沢でみなさまと議論できることを楽しみにしていますので、ぜひ会場にお越しいただき参加いただければ幸いです!